賃貸契約に必要な「連帯保証人」。その役割や頼む人の条件とは

物件の申込書にある「連帯保証人」の欄が埋まらず、悩んではいませんか?
この「連帯保証人」とは、入居者の代わりに家賃などの責任を負う人のことで、誰でも良いわけではありません。
入居者と同じ責任を負わなくてはいけないため、両親のいずれかに「連帯保証人」になってもらうケースが多いです。
場合によっては親族の誰かにお願いすることもできるので、「連帯保証人」の役割について知っておき、どんな人に頼んだら良いのかを決めておくと良いでしょう。
ここでは、「連帯保証人」の役割を「保証人」の場合と比較しながら見ていきます。
また、「連帯保証人」を頼む人の条件、必要性について詳しくご紹介します。
Contents
「連帯保証人」とはどんなもの?入居者に代わり責任を負う人
一人暮らしでお気に入りの賃貸物件が見つかったら、契約を結びます。
そのときの手続きでは、ほとんどの物件で「連帯保証人」を立てるよう求められます。
では、「連帯保証人」とはどんな人のことを言うのでしょうか。
「連帯保証人」について知るために、「保証人」との違いを見て比べてみましょう。
「保証人」と「連帯保証人」との違い
「保証人」も「連帯保証人」も入居者(借主)が家賃を支払えなくなった場合に、代わりに支払いをする点では同じです。
しかし、持っている権利が違います。
たとえば、大家さん(貸主)から家賃の請求を受けた場合、「保証人」であれば「入居者(借主)に先に請求してください」と、保証人としての支払いを一旦断ることが可能です。
一方、「連帯保証人」には断る権利がなく、その時点で入居者(借主)に代わって支払いをしなくてはいけません。
専門用語を使うと、「催告の抗弁権」という権利がありません。
他にも、以下のような違いがあります。
【支払い能力がある入居者が滞納し、「保証人」や「連帯保証人」に請求がきた場合】
- 保証人…「入居者は支払い能力があるので、自分は代わりに払いません」と言える
- 連帯保証人…保証人のように言う権利(検索の抗弁権)がない
【入居者の代わりに具体的な借金額を「保証人」や「連帯保証人」が支払う場合】
たとえば、入居者が100万円の借金をしたとしましょう。
このとき、複数の「保証人」や「連帯保証人」を立てていたなら、それぞれの負担額が異なります。
- 保証人…複数の保証人で100万円を分割して支払いができる
- 連帯保証人…複数の連帯保証人で分割することができない(全額一人で支払う)
このように、「保証人」と「連帯保証人」では、持っている権利が違い、借金の返済をするうえで、「連帯保証人」の方が責任は重いといえます。
賃貸物件を契約するときに、重い責任を負う「連帯保証人」になる人には、いくつかの条件があります。
「連帯保証人」になるための条件
連帯保証人として、入居者に代わってお金を支払える能力のある以下のような人が求められます。
- 親族(一般的に三親等以内※)
- 定期的な収入がある(職に就いている)
- 常に連絡が取れる
※三親等に当たるのは、おじ・おば、甥・姪、曾祖父母まで
実の父親でも、無職で収入が無くては連帯保証人として認められないことがあります。
連帯保証人を立てるときは、親族のなかで一番収入のある人になってもらうと良いでしょう。
なぜ必要なの?一人暮らしで「連帯保証人」を立てる必要性
そもそも、「連帯保証人」はなぜ必要なのでしょうか。
「連帯保証人」がどんな人かを見てきた中で、「入居者の代わりに支払うお金を保証する」役割があるのがわかります。
賃貸物件の部屋を貸している大家さん(貸主)は、入居者の家賃が収入源です。
もし、入居者(借主)が家賃を滞納したり、失踪したりしてしまうと、大家さんはその分の収入を得られません。
毎月入るはずの収入が途絶えたら困ってしまいますね。
家賃滞納が長期に渡ると、大家さんの生活が苦しくなってしまうおそれがありますが、大家さんが一方的に入居者に対して契約を解除することはできません。
大家さん(貸主)から契約を解除する場合は、「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」と言う法律で、以下のような一定の決まりがあります。
- 期間満了の1年前~6ヶ月前に、借主に更新しない旨を通知すること
- 解約申し入れを行うこと
- 解約申し入れから6ヶ月を経過すること
- 正当な事由があること
これらの決まりのもと、契約解除へ至るには時間がかかり、なかなか難しいものです。
そのため、大家さんが安心して物件を貸すためには、毎月の家賃の支払いを保証できる「連帯保証人」が必要なのです。
「連帯保証人」については、民法の制度(連帯保証人制度)としても定められており、大家さんの家賃収入を守り、何かあったときの修繕費用や損害費用を回収するためにも必要です。
2020年4月から、連帯保証人が責任を負う限度額を(極度額)を契約書に明記することが必要となりました。
そのため、保証額の限度が視覚化されて、連帯保証人の責任が見えやすくなりました。
賃貸契約に必要な「連帯保証人」になってもらう人には、負う限度額を伝えてお願いすると良いでしょう。
事前の準備が大切!「連帯保証人」を立てるときに必要なもの
契約するときの手続きで、入居予定者が行うのが、「入居申込書の記入」です。
氏名や住所、連絡先のほか、連帯保証人を書き込む欄があります。
連帯保証人を立てるときには、その人の氏名、住所、連絡先、勤務先、年収、勤続年数なども記入しなくてはいけません。
そのため、あらかじめ連帯保証人になってくれるか相談し、承諾を得たら必要事項を聞いておくと良いでしょう。
他に、連帯保証人に関する以下の書類が必要となります。
- 連帯保証人の住民票
- 連帯保証人の印鑑証明書
- 連帯保証人の承諾書
- 連帯保証人の収入証明書
必要書類が揃わないと、何度も不動産屋さんに足を運ばないと行けなくなるので、どの書類が必要かをしっかりと確認して、契約までに用意しておくようにしましょう。
「連帯保証人」を頼める人がいない時は保証会社にお願いしよう
「保証人になってくれる人がいない」、「支払い能力のある近親者がいない」など、連帯保証人を立てられない場合は、保証会社に連帯保証人の役割をお願いすることができます。
保証会社も連帯保証人と同じように、入居者が家賃を支払えないときに代わりに家賃を保証してくれます。
ただ、保証会社の利用には、保証料の支払いが必要です。
保証料は、利用する保証会社によって違いますが、家賃1ヶ月分の半分~全額が目安です。
また、1、2年ごとに1万円ほどの更新料を支払います。
どうしても連帯保証人を立てられない場合は、物件の契約時に相談の上、保証料を支払って保証会社に連帯保証人の代わりをしてもらうと良いでしょう。
連帯保証人を立てて、家賃未払いによるトラブルを回避しよう
賃貸契約の際に必要な「連帯保証人」について見てきましたが、いかがでしたか?
大家さんと入居予定者が安心してスムーズに契約をするためにも、家賃を保証してくれる「連帯保証人」の存在は大きいです。
今回ご紹介した「連帯保証人」について、もう一度振り返ってみましょう。
●大家さんからの請求を断ることができない
●入居者に支払い能力があっても、請求を断ることができない
●複数の連帯保証人で分割して支払うことができない
【連帯保証人になるための条件】
●親族(一般的に三親等以内)
●定期的な収入がある(職に就いている)
●常に連絡が取れる
【連帯保証人を立てる必要性】
●大家さんが安心して物件を貸すために必要
【連帯保証人を立てる時に必要な記入事項と書類】
〈記入事項〉
●連帯保証人の氏名
●住所
●連絡先
●勤務先
●年収
●勤続年数
〈書類〉
●連帯保証人の住民票
●連帯保証人の印鑑証明書
●連帯保証人の承諾書
●連帯保証人の収入証明書
一人暮らしで賃貸契約をするとき、大家さんは入居予定者を信頼してお部屋を貸してくれます。
そこで、連帯保証人として身近な人を立てると、入居者への信頼はさらに強くなり、入居審査を通りやすくなります。
一人暮らしでは何が起こるか分からないもの。
家賃が払えなくなってしまっても、連帯保証人の存在が大家さんにも入居者にも安心感を与えてくれます。
賃貸契約では、できるだけ近親者の連帯保証人を立て、今後の家賃未払いトラブルを未然に防ぎましょう。
連帯保証人が見つからない場合は、保証会社を検討してください。
お気に入りの物件に住むためにも、連帯保証人への交渉や、保証会社の利用検討を頭に入れておき、スムーズに契約を進めていきましょう。
一人暮らしルーム公式アカウント
Instagramで素敵な一人暮らしのお部屋写真を紹介しています。
「#一人暮らしルーム」のハッシュタグをつけて投稿してください。
紹介時にはスタッフからご連絡後、皆様の写真を掲載させていただきます。
あなたのお気に入りのお部屋をぜひ投稿してください!
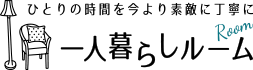



あなたのコメントをどうぞ!